|
|
|
|
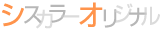

|
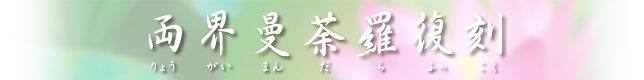
|
|
|
 |
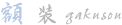 |
|
|
 |
【概 要】曼荼羅 … 両界曼荼羅・『胎蔵界曼荼羅(たいぞうかいまんだら)』と『金剛界曼荼羅(こんごうかいまんだら)』
◆密教のさとりの境地、胎蔵界(理)と金剛界(智)◆
曼荼羅とはサンスクリット語(梵語)を音写した言葉で、『本質をもつもの』『本質を図示・図解するもの』の意味です。経典が文字を通してさとりを説いているのに対して、曼荼羅はそのさとりの内容を図絵にして表わしたものといえます。
空海は31歳の時に唐(中国)へ留学し、恵果阿闍梨(けいかあじゃり)より密教を学び継承、806年に帰朝した際に多数の書物とともに曼荼羅を持ち帰りました。胎蔵界と金剛界の曼荼羅を合わせて両界曼荼羅といい、真言宗や天台宗では礼拝対象や修法の本尊として主に堂内にまつられます。東の壁面に胎蔵界(上が東)、西に金剛界(上が西)を掛け一対としますが、本来二つの曼荼羅は胎蔵界は『大日経』、金剛界は『金剛頂経(こんごうちょうきょう)』という別々の経典に基づき、考えの異なるものでした。二つの曼荼羅を一対としたのは空海の師の恵果といわれています。
真言宗では、胎蔵界曼荼羅を理(現象世界を貫いている普遍的な理法)、金剛界を智(真理を悟る仏さまの智恵)の象徴とみなし、二つを一体のものとします。また、曼荼羅は大変色鮮やかに描かれていますが、これは密教の教理を象徴的に示したものといえます。胎蔵界の中心の赤い蓮華は仏さまの大慈悲を示し、金剛界は白を基調に仏さまは白い月輪(がちりん)の中に描かれ悟りの智恵を表しています。
◆胎蔵界曼荼羅の構成◆ ※下図参照
胎蔵界曼荼羅は十二の院で構成されています。
中央の中台八葉院(ちゅうだいはちよういん)には、中心の大日如来の周囲に宝幢如来(ほうどうにょらい)/東、開敷華王如来(かいふけおうにょらい)/南、無量寿如来(むりょうじゅにょらい)/西、天鼓雷音如来(てんくらいおんにょらい)/北という四仏と、普賢菩薩(ふげんぼさつ)/東南、文殊菩薩(もんじゅぼさつ)/南西、観音菩薩(かんのんぼさつ)/西北、彌勒菩薩(みろくぼさつ)/北東という四菩薩が座しています。
中台八葉院を囲む初重、東の遍知院には一院と6尊、西の持明院は5尊、北の蓮華部院は36尊、南の金剛部院は33尊描かれています。
二重目の東の釈迦院には39尊、西の虚空蔵院は28尊、北の地蔵院は9尊、蘇悉地院は8尊、南の除蓋障院は9尊。
三重目の外金剛部院には、東方39尊、南方62尊、西方48尊、北方53尊で計202尊で、胎蔵界曼荼羅は全部で410尊の仏・菩薩・天で構成されています。
|
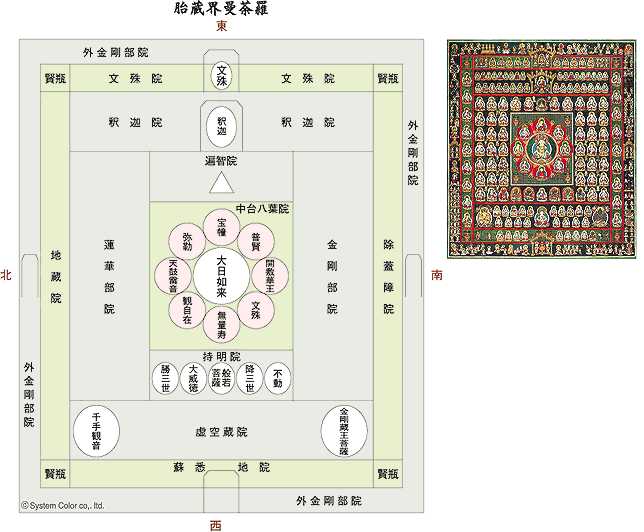
|
◆金剛界曼荼羅の構成◆ ※下図参照
金剛界曼荼羅は九つの区画=九会(くえ)をもち、各名称は中心が「成身会(じょうじんえ)」、その下に「三昧耶会(さんまやえ)」、その左に「微細会(みさいえ)」、その上に「供養会(くようえ)」、その上に「四印会(しいんね)」、その右に「一印会(いちいんね)」、その右に「理趣会(りしゅえ)」、その下に「降三世会(ごうざんぜえ)」、その下に「降三世三昧耶会(ごうざんぜさんまやえ)」といいます。
「成身会」は中心の大日如来(図中番号=1)を阿閃如来(あしゅくにょらい、図中番号=2)/東、宝生如来(ほうしょうにょらい、図中番号=3)/南、無量寿如来(むりょうじゅにょらい、図中番号=4)/西、不空成就如来(ふくうじょじゅにょらい、図中番号=5)/北の四仏が囲みます。この五仏をそれぞれ四菩薩(四親近菩薩、ししんごんぼさつ)が囲んでいるため、合わせて16大菩薩がいます。その対角の四隅に「内の四供養菩薩」と呼ばれる菩薩がいてこれで大金剛輪を構成し、この輪を四角に囲んで「賢却千仏(げんごうせんぶつ)」という千体仏が描かれています。その対角の四隅に「外の四供養菩薩」、東西南北の四方に「四摂菩薩(ししょうぼさつ)」、さらにその外側の外金剛部院に20天、合わせて1061尊で「成身会」は構成されています。
「三昧耶会」は73尊、「微細会」は37尊、「供養会」は73尊、「四印会」は13尊、「一印会」は1尊、「理趣会」は17尊、「降三世会」は77尊、「降三世三昧耶会」は73尊、金剛界曼荼羅は全部で1461尊の仏・菩薩・天で構成されています。
|
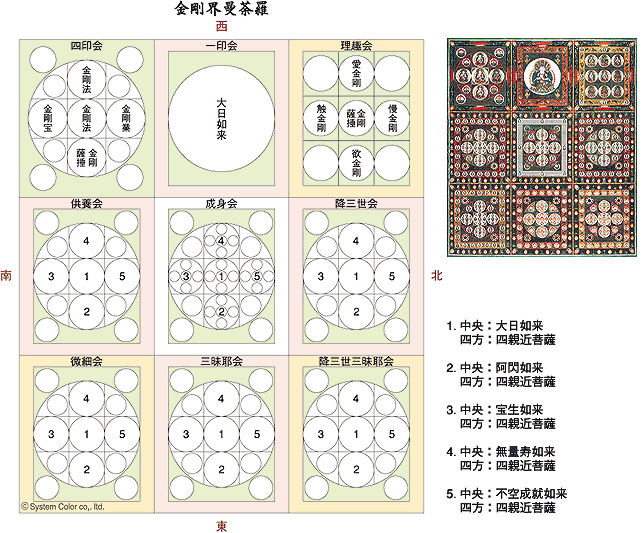 |
 |
 両界曼荼羅図/商品一覧へ 両界曼荼羅図/商品一覧へ |
 このページの先頭へ このページの先頭へ |
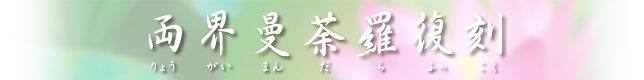
|
|
|
 |
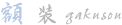 |
|
|
 |
  |
 このページの先頭へ このページの先頭へ |
|
|
 |
| | 会社概要 | 特定商取引法に基づく表示 | 個人情報保護方針 | サイトマップ | リンク | お問合せ | |
|
株式会社システムカラー  地図 地図
〒530-0047 大阪市北区西天満5丁目1-19 高木ビル1F
TEL:06-6314-1516 FAX:06-6363-1428
Copyright (c) 2024 System Color co.,ltd. All rights reserved. |
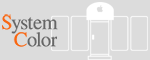 |
|